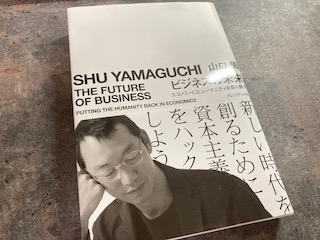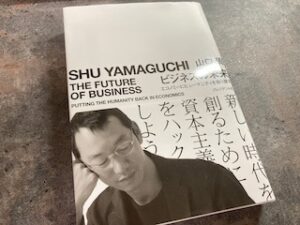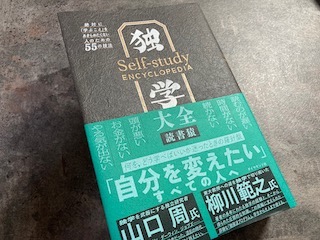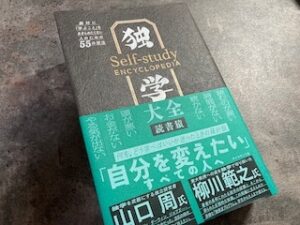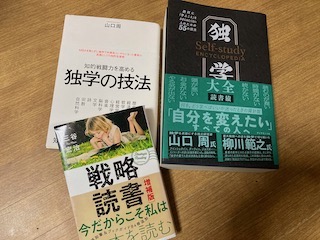先日の慶応MCCの夕学五十講で小林武彦教授による「生物はなぜ死ぬのか」という講義を受けてきました。

研究に人生を捧げる方とはこういう方をいうんだなぁ・・としっくり。ご自身が興味ある研究の話題を語られる姿がキラキラとまるで少年のようでした。
■ 全ての生物は死ぬ、死ななくてはいけない
■ なぜなら死ぬことが進化には必須だから
■ 死は個体にとっては終わりだが、進化にとっては始まり
■ 進化とは、変化と選択の繰り返しの結果であって目的ではない
■ その進化の結果として、たまたま私たちがここにいる
脳のあちこちが刺激されるあっという間の2時間でした。
自分達がどこから来て、どこに向かう・・みたいな話でもあったのかなぁと。地球という星の表面にへばりついて進化してきた一生命体と自己を捉え直してみました。
そうした思考は長くは続かないのですが、日々の喧騒から離れて思索の海に泳ぎ出す貴重な機会。
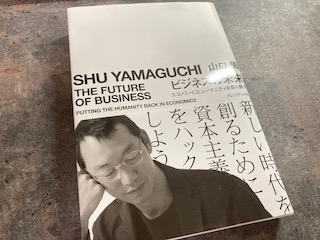
ビジネスはその歴史的使命を追えつつあるのか。
切れ味鋭い論考が魅力の山口周さんの著作で現在と未来を見つめ直してみます。こうした深い問いに向き合うためには知的体力と教養が必要なんだろうなぁ、、と思いつつ。
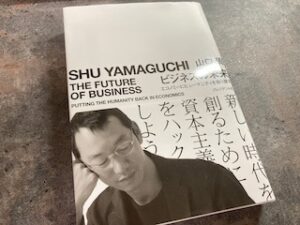
「生きがい」や「幸福」というものを追求するということも社会課題であり、この解決に向けて動くことは、今まで以上に人生の一大事となりそうだな・・との思いを深めました。
様々な論点やヒントに本作も溢れているのですが、自分が今回改めて気になったのはユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)の是非についての部分。
UBIとは「文化的で健康な生活を維持するのに必要な金額を、無条件で、全国民に対して、給付する。」という制度のこと。UBIの導入は、山口さんが考えるように、本当に、貧困の解消や格差の是正にとどまらず、ライフスタイルの多様化や社会的イノベーションの促進につながるのか。
感覚的には資本主義を否定した社会主義的アプローチのようにも思いますが、むしろ労働市場に徹底的に市場原理を働かせることになると言われると、確かにそうなのかもしれない・・とも。
たまたま偶然に選んだ仕事にやりがいも感じている自身の幸運には感謝しつつ、それでも未来の社会に思いを馳せるのは、やはり子供を授かり、自分の人生より先の時間軸を意識するからかもしれません。
どうやっても最低限生きていける社会において、それでもやりたいことはなんでしょうか。
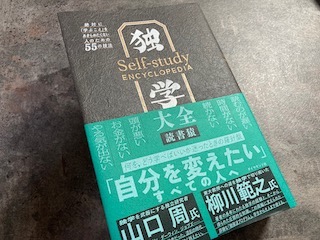
独学するヒトでありたいと思います。
年初に、濫読の中に教養を学べる本も入れていこうと思い立ち(→今年は教養本を50冊〜読書戦略2021)、4月からは慶應MCCの夕学五十講も活用してライブ体験でも脳に刺激。
これまで受講したのは・・Well-beingの石川善樹さん、田端大学塾長の田端信太郎さん、島田由香さん、そして萱野稔人さんと財務官僚お二人の鼎談の4つのご講義。それぞれに異なる刺激を頂いて、理解が足りない部分は著作を読んだりしながら独りで補完。
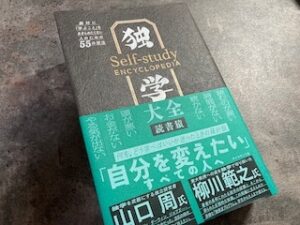
(方法論も整理しておこうと、じっくり通読)
2021年後半は少しテーマを自分なりに設定して、掘り下げていくアプローチも開始してみようかと考えています。
小説ジャンルでは年初から追いかけ始めたSFを継続するとして、それ以外で気になるのは・・定番の哲学とかですかね、完全なる初学者ですが。哲学とか歴史について知っていることを少しずつ増やし、頭の中で考える力を層状に醸成していきたい。
机の下の積読本の山は年内で一度一掃することも並行して課題目標(ジャンルはバラバラなので濫読ですね)。手元の未読の山は常時20冊以内ぐらいに抑えて回転鮮度をあげたい気がします。
学び続けることは、うまく学ぶことよりもずっと難しく、また遥かに重要である。(「独学大全」読書猿 著より)
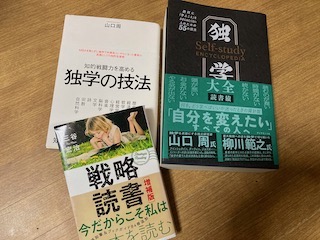
本ブログはライフログとして記憶力弱体化の一途を辿る自分の外部補助記憶メモリーチップの地位を確立して久しいですが(実に10年超)、今後はラーニングログとしても活用を試みます。
具体的には「独学のススメ」や「コツコツ語学」、「一流ビジネスマン研究」を定期的に更新していこう・・というものです。
これらは全て「自己実現マニア」からの派生ですが、「独学のススメ」には広く教養系、「コツコツ語学」は語学特化、「一流ビジネスマン研究」はビジネスパーソン的な話題や私的な研究を拾っていければ・・と思います。定期的な更新がないのは時間を使えていない、、という客観的指標にもなるということで。
現代事情に照らせば、動画によるvlogとかになるのでしょうが、それはまだ相当に億劫なので、、取り敢えずはブログで。
ラーニングログとは、航海日誌であり、ペースメーカーでもある、、と読書猿さんは定義しています。「記録を取るものは向上する」という言葉を信じて独学者としての長い旅(航海)を続けたいと思います。
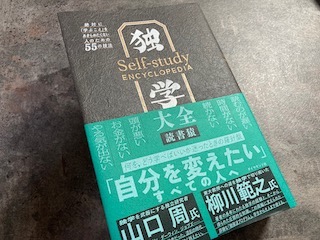
独学するヒトでありたいと思います。
勿論、誰かに習った方が効果があったり、近道となることについてはその限りではありません(独学という手法に拘るわけではなく、学ぶことに拘りたい)。独学の魅力はいつでもどこでも始められること。そして何を学ぶかが大事というより、学び続けることが大事・・という真理とも相性が良いことと感じています。
振り返れば独学っぽいものに取り組み始めたのは大学時代、それも5年生あたりだった気がします。自主留年という暴挙に出た大学5年の自分には週1回のゼミ以外、一つも必修授業がない夢の1年間が広がってました。(経緯については割愛・・と思ったら、12年も前に少し書いた→人生の岐路となった1997年)
生活費を稼ぐためのバイトは午後から、趣味の活動以外はほぼ自由・・というモラトリアムな日々。そんな中で自分は午前中を自主的に学んでました。今思えば大した学びではありませんでしたが(今もですが・・)誰に言われるのでもなく自主的に、という点が独学を志す「発心」というスタート地点。
自分がなぜ学ぼうと思ったのか・・そのきっかけや動機は今もって不明瞭なのですが、ゼミの先輩が将来の就職への不安を覚えながら(文系院生あるあるですが)、日夜、自身のマイルールに従って激しく学ばれていることを伺った際にドキッと刺激を受けたことを覚えています。
2021年は教養を意識して自身の知の骨組みや厚みをしっかりとしたものに組み直したいという思いがあり(→今年は教養本を50冊〜読書戦略2021)、このモメンタムは大事にしたい。(日々の雑事に溺れがちなので)
今は7頭の牛も幸いに太っていますが、痩せた牛が大量に攻め寄せてくるかもしれない。
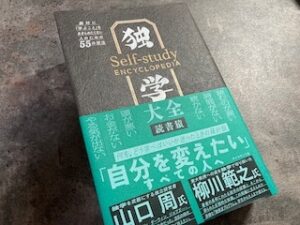
(一度バラバラと拾い読みした本書を、改めて頭から順に読み進めています、知の羅針盤の獲得のために)
学び続けることは、うまく学ぶことよりもずっと難しく、また遥かに重要である。(「独学大全」読書猿 著より)
よく食べ、よく飲み、よく踊る、中年男子のライフログ〜人生の達人を目指して生きてます。2024年〜ロンドン在。