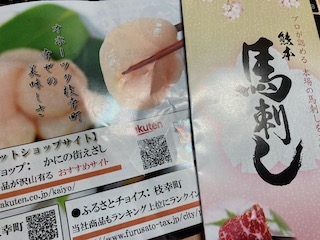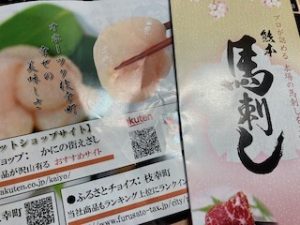この2ヶ月ほど取り組んできた支出の最適化(節約と倹約)プロジェクトもそろそろ奥の院である最大の変動費に向かい合う時期となってきました。
私の飲み代も含め、これまで整理が適当だった「食費」カテゴリ。自ら真剣に事実を直視することを恐れていたとも。。

(魚介で有名な居酒屋チェーン魚金を久しぶりに再訪)
まずはあらためて、正確な実態把握ということで、食費としてマネーフォワード上で自動集計されていた野放し状態を見直し、カテゴリの中分類を正確にふり直すことからスタート。(暇な時に少しだけやっていましたが正確性と一貫性に欠けていたので)
食費に放り込まれていた費用は以下の4つの既存の中分類に。
・食料品(家族での自炊コスト)
・外食(家族での外食費、自分がメンバーに含まれない場合も)
・昼ごはん(私の出勤時の昼食代、飲み代と区別するために)
・カフェ(ラテマネー抑制の目安として)
私の飲み代は交際費(飲み会)に移動。(クレジットカードの履歴から食費に自動的に振られておりました)まとめて払う場合も多いので、この出費総額がイコール飲み代ではないのですが、現金として回収した分もいずれ飲み代に使った可能性が高いと思うので一部だけを昼ごはんに切り出して整理。
どうやら、2019年5月以来の日本の生活費の全容が見えてきました。(長くなったので続く)