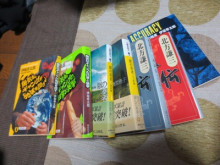痩せたい・・・といいながら、ちゃんこ食べてる場合じゃない。

築地のちゃんこ屋さん「佐賀昇」さん、ちゃんと番付表に載っております昭和63年の。何とも懐かしい皆さんですね、千代の富士に北勝海、そして大乃国に小錦。

やっぱり美味しかった。。 (柚子胡椒はミラクルスパイス!)これで明日も増量か。。
帰宅してからいそいそと明日からの沖縄旅行準備。いやーテンションあがります。
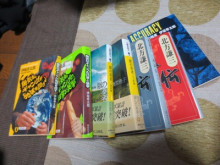
(4泊5日なんで、文庫分は7冊ぐらいでいいかしら)
それでは沖縄での美味しい食事レポートは、東京に戻ったらまたアップするという事で。5日間ほど心身のリフレッシュ&家族サービスして参ります。
では!
弟の30路ベンチャーの業績報告を聞く定例の株主総会。5月末をもって、第2期が終了。
現在、決算作業中ですが、話を聞く限りではどうやら黒字になりそうな様子です。まだ上京して丸2年、試行錯誤しながらと考えればなかなかのもの。

二年目からはじめた業務用アプリ開発の孫請け、これが仕事のベースになっています。やはり食べていくには B to B が一つ手っ取り早いと思います。 Cは難しい。
ここで事業の土台を固めながら、如何に自社開発アプリで攻め込んでいくか。失敗や、見通しの甘さも経験しながら、弟のビジネス思考力は確実に上がってきています。
2年間で方向性の異なるアプリを3本世に出してみて、色々わかったことがあります。(僕自身も)大企業が攻めて来ない規模で、且つその他中小に技術優位性のあるブルーオーシャンを目指すには。
5歳上の兄として、簡単に負ける気はしませんが、なにしろあちらは社長として経験値荒稼ぎ中。今後も、実年齢以上に、ビジネス経験の差をはっきり示せるように、自分も負けずに成長しないと。
そして株主とては最後に一言。
早く、じゃんじゃん配当出来るようになりなされ。
イギリス&スペインの友人夫婦を自宅にお招き。(先日は西麻布の新居を堪能させて頂きました、主に赤ワインで泥酔)
まずは、東京の西の下町的な空気感を楽しんでもらおうと近所の生鮮市場にご案内。スペインの奥様、新鮮な野菜の値札を見ながら大興奮。


ポロネギ 1本280円を手にとって、「これ西麻布で700円だったわ!!」って。。さらに本日の閉店前のお買い得品の小松菜10円で絶句。「テンよ、テン!!」
うれしそうに3,000円分ぐらいの大量の野菜と果物を買い込んでました。いやー、案内した甲斐がありました。

娘二人もすっかり自宅で意気投合。特にうちの娘がジュリアにぞっこんLOVE。

(鼻も低いし、顔もぺったりで日本人の子だなぁ)
大人は大人で、築30数年の木造家屋のボロい佇まいがたまらないらしく、大喜び。これぞ日本が誇る伝統的家屋です、火事がきたらイチコロさ。

(太鼓など興味津々な日本グッズを色々登場させて遊んでもらいました)
料理はちょっと手抜きで、外で一緒に買ったモツ串や、刺身なんかと一緒に普通のお惣菜。お酒は勿論、日本のビールと日本酒。


デザートで出したメロンやびわという、日本が世界に誇れる果物も喜んで頂きました。せっかくの日本駐在の機会、存分に日本の生活を楽しんで欲しいと思います。
福島産のニラが3把で100円のままなのを見ると悲しくなります。我が家で買うぐらいでは、とても買いきれない。

■ No. 039 贅沢にら玉豚
自分のポイントはとにかく卵は半熟ドロドロで。熱いご飯の余熱でようやく軽く火が通るぐらいが好み。

■ No. 040 帆立ヒモ炒め
帆立のヒモだけとか、烏賊のゲソと肝だけとか、捨て値で売っているのをすかさず購入。なんでここを食べないのかと酒飲みとしては疑問百出。
旦那ご飯だけ掲載していると、まるで妻が料理をしてないように錯覚しますので公平に。平日、妻の手料理を楽しみに、小説を読みふけりつつ帰宅するのが庶民の幸せってもの。

(この日は鶏の特製みぞれ鍋が秀逸)

(グリーンカレー鍋・・・グリーンカレーとの違いは不明、でも美味)
社内向けの研修で、講師をする機会がありました。100人弱を前にして話すなんて・・・自分の披露パーティー以来です。

(6ヶ月前の娘、、、歩き回るようになって今はとても痩せました)
資料も入念に直前まで作りこみ、リハーサルもしたのですが、やはり本番は本番。自分で気が付いて軌道調整するまで、ちょっと早口だったなぁと反省も。
身振り手振り、目の配り方、声の抑揚や話し方の間など、色々コントロールしたいものの実戦では全てがやはり思う通りにはならないなぁと感じました。
良かったよ!という声を結構かけてもらいましたが、自分では、まだまだ及第点レベル。やはり場数を今後もっと踏んでいかなくては!
よく食べ、よく飲み、よく踊る、中年男子のライフログ〜人生の達人を目指して生きてます。2026年〜中国在住。