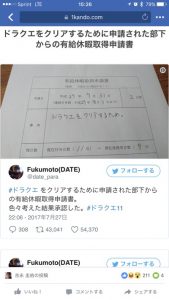妻子が帰還する前日の話。(件名は純文学風)
少し早めに帰宅し部屋着に着替えたところで玄関のチャイム。すりガラスから外を眺めると誰か女性が立っております。夕方に誰だろう、近所の人かな?
玄関をあけると(正確にはうちは裏口となるガレージをあけると)、見知らぬ中国系女性。そして手には・・・鎌。
鎌!?
開口一番「Do you speak Chinese?」「・・・No」
どうやら鎌でいきなり襲ってくることはないようでホッと一息。銃社会の米国で鎌で襲われたら事件だわぁ・・とかボンヤリ考えてしまいました。
聞けば裏のお隣さんで、我が家の裏庭まで侵入しているWater Melonを収穫したいということ。あぁ、最近よく見ていなかったけど、来てた、来てた、なんだか蔓が。おばちゃん、スタスタと裏庭に入っていき、Water Melonをばっさりと鎌で収穫。これはメロンというか瓜、冬瓜の類ですね。
じっと見守っていたら、煮ると美味しいよと半分くれました。

(すごく産毛がチクチク、さっきまで生きてたから)

(マウスと比べると、でかい・・・・)
やはり冬瓜でいいのかなぁ。調べてみると冬に収穫ではなくて7〜9月が収穫時期なんですね。初めての冬瓜ですが、皮を剥いて、真ん中の種のところも取って、ダシ袋と一緒に水から単純に煮てみました。

(結構な量を水から)

でけた。
あついところを、アチアチといいながら食べても良いですし、冷蔵庫で冷やして食べるのも美味しかった。これまでレパートリーには全くなかった野菜なので、今度Ranch Market(中華系スーパー)で仕入れて何品か作ってみたいと思います。煮るのは勿論、炒めてもいけそう。
裏のおばさんにその後美味しく食べたお礼を伝えると、いまなってる瓜もあと1週間ぐらいで食べ頃になるから、自分で収穫してまた食べなさいと。

(これのことか・・)
これで裏の家とも瓜を通じて交流開始か。



















 (猫じゃなくても美人)
(猫じゃなくても美人)