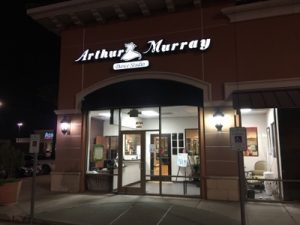来年以降の目標設定を考える中で、やはり中長期の視点での習慣整備が必要だなと感じています。特に全ての活動の土台となるカラダ、健康。

(先日、家族に43歳到達をケーキと共に祝って頂きました)
これまで自分のバケットリスト(俺のバケツ)には、健康・カラダ系の願いには、
■ 12. 見た目年齢、実年齢マイナス5歳以上を維持
というものが入っていました。これすらなかなか挑戦的な目標ではありますが、夢はもう一段大きく、今から50年、しっかり健康に生きるための体づくり、というものを考えてみたいと思います。
■ 16. 死ぬまでしっかり活動可能なカラダ作り
目標達成には一定の運動習慣のインストールは勿論ですが、食事や睡眠への取り組み、根っこからの意識改革がより重要な気がします。
睡眠については負債返済を意識してから、活動時間は減ったものの起きている時間のパフォーマンスは上がった気がします。(→睡眠負債の返済開始)
■ 17. 睡眠負債を貯めない
ここに多少行き当たりばったりな食事習慣見直しと、なかなか定着しないカラダづくり系の習慣導入、10年近くもがいている公開減量生活の結果実現・・などの諸活動をうまく統合していければと思います(今度こそ着実に)。

人生100年時代・・にはあと7年届かない計算ではありますが、93歳まで50年、自分にとっては十二分に高い目標設定で・・ワクワクします。
細かな作戦の肉付けはこれから。(おっと、カラダへのこれ以上への肉付けは厳禁)