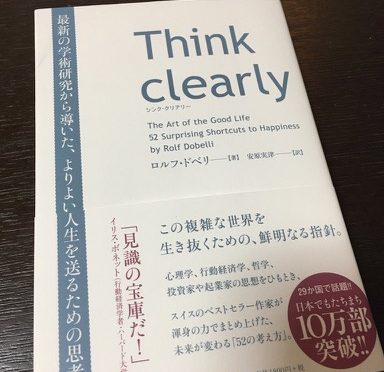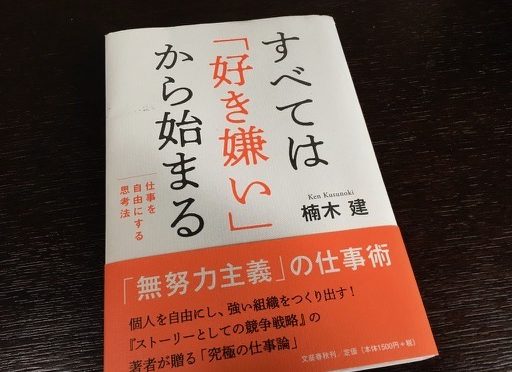「Think clearly」。副題は、最新の学術研究から導いた、より良い人生を送るための思考法。
スイスのビジネスマン上がりのベストセラー作家の方がまとめた52の考え方。(ご自身で「思考の道具箱」と呼んでます)
52はちょっと道具としてはいかにも多いので厳選して7つほどを自分の人生に取り入れ、日々を上向かせてみたいと思います。
■ 考えるより、行動しよう
■ なんでも柔軟に修正しよう
■ 目標を立てよう
■ 自分と波長の合う相手を選ぼう
■ 解決よりも、予防をしよう
■ 世界を変えるという幻想を捨てよう
■ 自分の人生に集中しよう
それぞれのメッセージをリライトしてストーリーにするとこんな感じか。
考えるだけの方がラク、行動する方が難しい。人生で自分が何を求めているか知るためには、色々やってみるしかない。これは自分を知るための一番の近道。
始めることが出来たら次はいかに修正するか。物事が計画通りに進むことなんてありえない、ということ。不都合な現実から目を背けずにひたすら軌道修正、方向修正。
それでも、目標がなければ、それを達成することは決して出来ない。人生の大きな意義の答えを探すのは難しいが、小さな意義、個人的な目標を追うことには意味がある。人の幸福度は所得の額ではなく、どれだけ目標を達成出来たかどうかで決まる。
自分は変えられても、他人は変えられない。好感をもてて、信頼できそうな相手としか付き合いわない、仕事もしない、これも凄く重要な人生への向き合い方。
人生の困難は解決するよりも、避ける方が早い、という記述は響いた。賢明さとは予防的措置を施すこと。確かにその通りだ。何かが起こってから対処するよりも、起こさない方がきっと簡単。
そして、何者でもない自分を受け入れること。世界?変えられるはずがない。それよりも、自分の人生に集中しよう。今この時に集中し、一日一日を良い日として過ごすにはどうすれば良いか。
内なる成功を目指し、平静なる心を身につければ、きっと良い人生が送れる。良い人生を「穏やかに、かつ軽やかに流れる人生」と表現したのはストア派の哲学者エピクテトスだとか。
さて、考えるより実践、実践。